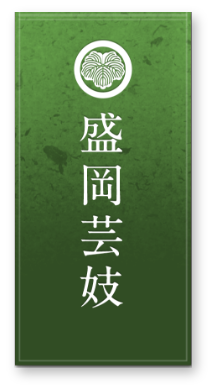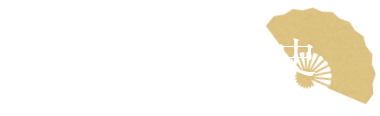盛岡芸妓の歴史
明治の初め頃、町の中央を流れる中津川を中心に、花街はすでに八幡町と本町に分かれていました。それぞれ幡街(ばんがい)、本街(ほんがい)と呼ばれ、幡街は主に商家のだんな衆が、官庁街である本街は主に役人や政治家が利用していたことから、幡街芸妓と本街芸妓は気質も違い、ともに芸を競い合っていたと言われています。
明治25年から28年まで盛岡に滞在していた名人・常磐津林中から手ほどきを受け、その後も林中の縁で邦楽・邦舞界の第一人者からの指導を受け続けている両街の芸妓衆は、その芸の質の高さで全国に名をとどろかせてきました。
明治41年東北6県連合共進会演芸の部で優勝。隆盛期の明治44年正月の新聞広告によると盛岡の芸妓総数は95人(八幡54人、本町41人)で料亭の数も19亭あったといいます。
大正2年には活躍の場である盛岡劇場が開場。大正6年、東京の三越の東北名産陳列会の余興でも大評判をとります。
戦中の歌舞音曲・料亭営業禁止を乗り越え、戦後に復帰。親子2代3代で活躍する芸妓も多くなります。柳橋や新橋、芳町に向嶋など、同じ芸事の花街とも交流が深まりました。
全国花街芸妓合同公演の紅緑会には4回出演。特別章や文部大臣奨励賞邦舞の部を受賞しています。
しかし、世情や経済情勢の変化などで全国的にも花柳界が衰退する中、盛岡でも盛岡芸妓の活躍の場である料亭が次々と廃業し、芸妓の人数も減ってきました。

新盛岡芸妓誕生
盛岡市では盛岡芸妓の衰退を危惧し、次世代へと盛岡芸妓文化が受け継がれるよう平成22年2月、伝統芸能継承活用事業(ふるさと雇用)を活用し、3名の見習い芸妓を採用しました。平成24年4月からは、生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業の活用へと変わりましたが、3名が見習い芸妓として日夜稽古に励んできました。
平成24年7月末日をもって1名が辞めることとなりましたが、平成24年10月20日に盛岡芸妓として「富勇」、「とも千代」の2名が誕生しました(平成30年11月18日、とも千代引退)。

盛岡芸妓見習い「ひよ妓」の育成
盛岡芸妓文化の伝承・継承を図るため、平成27年度から盛岡芸妓後援会は盛岡市からの補助を受け、同年9月から2名の盛岡芸妓見習い「ひよ妓」の育成を開始。
平成28年6月に、ひよ妓としてのお披露目の会を開催し、それぞれ「喜久丸」「まり佳」の芸名を発表(令和元年、都合により「まり佳」育成辞退)。
その後先輩お姐さん方の指導のもと熱心に稽古に励み、令和2年8月1日に「喜久丸」が盛岡芸妓として一本立ちしました(令和4年10月、喜久丸引退)。